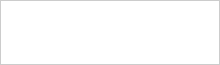会長
実体験を学習に(会長ブログ)
2014年11月8日会長
さて学習共同体の一斉指導教室で行われる理科実験には塾生のお友達、すなわち塾外の生徒さんも参加することができます。写真は今年の理科実験の様子です。
実際に目で見、手で触れること、試してみること、そして考えることが大切なことを実体験してもらいたいと考えています。その時にいろんな工夫ができればもっと素晴らしい体験になります。
小学校3年生の時に夜咲いて朝には閉じてしまう花を知っていた河浜は、どうして朝になったらこの花は閉じるんだろうと疑問に思いました。そんな話を母親にすると、母はさっさとその花を掘り出し、大きなポリバケツに植えかえて、押し入れの中に放り込んだんです。この花どうなったと思いますか?
そんな体験が、子供たちに、知識だけではなく大切な知恵を与えていくんだと信じています。 (写真4枚)




中3勉強合宿(会長ブログ)
2014年11月6日上中学院~戸坂出江 会長 河浜塾本部八幡校 河浜塾東原教室 河浜塾祇園西原教室
生徒たちには、通りすぎるだけの受験ではなく、自分に挑戦し、目標を掲げて頑張る経験をしてほしいんです。その努力が何かをなしとげた感動をうむんだと思います。
「努力は、感動の種まきです。」
ところが、このごろの中3生は、なかなか受験生になってくれません。そのゆるんだ心をひきしめるために、もう一度再スタートの合宿をするのです。
私たちは、合格のみを目指す「合格請負業」ではありません。もちろん、合格を目指します。ありがたいことに合格率も高いと思いますが、それより受験のプロセスを通して、人格的に成長してほしいと願っています。
「みんな! 努力家になりたまえ、努力の結果、感動の涙を流す人生を歩みたまえ、努力は感動の種まきだ。」 (写真4枚)




リンゴ
2014年9月5日会長
リンゴの この 大きさは
この リンゴだけで いっぱいだ
リンゴが ひとつ ここに ある
ほかには なんにも ないああ ここで あることと ないことが
まぶしいように ぴったりだ
ぞうさん、ぞうさん、おはなが長いのねの詩を書かれたまどみちおさんの詩だ。今年104歳の天寿を全うし、その年齢に似合わない新鮮な目を持ったまま逝かれた。
彼の目から見ると何かが「そこにある」ためには、何もない空間がそこにあり、その何もないところにすっぽりと何かが入っているということだというのだ。しかもその何かは1ミリも自分の占領する空間からははみ出していない。あることと無いことがぴったりでないとリンゴはその場から弾き飛ばされてしまうとでも言いたいのだろう。
だとすると私たちの肉体も空間の一部を占領しながら、私たちの体に合わせた分だけ、空間をあけていただいているのではないか。
自然というものや神という存在が、そうやって私たちに居場所を与え、私たちを守ってくださっているのではないか・・・。
それは、もしかしたらとても幸せなことではないか・・・あなたや私の存在はそうやって肯定されているのではないか・・そしてそれはとても感謝なことなのではないか。
私は存在する。その場所に他に何物もあることができない。自分のためだけの空間・・・あなたも私も存在することを許されている・・・。

学習共同体河浜塾「星降る一夜合宿」その2
2014年9月3日会長
平生、おとなしい男の子が、妙に包丁を使うのが上手だったり、炭火を起こすのが上手でみんなの喝采を浴びる子や小刀を使って次々に竹の節を削り取る子、皿洗いの天才少女まで登場しました。
子供たちはみんないろんな面を持っています。ほめてあげるところがいっぱいなんです。そんなところから生まれる小さな自信が、生きていく力になり、ちょっと嫌な言い方だけど学習にもいい効果をもたらします。
私の友人に一人の陶芸家がいます。小さい時はまるっきり勉強が苦手だったといいます。でも彼は一流の陶芸家になる過程で自然に多くの知識を身に着け、立派な文化人となっています。作陶することによる自信とより高い文化に触れる機会をもたらした環境の変化が自然に彼を学びに向かわせたんでしょう。「ぼくは〇〇が得意だ。そのお陰でいろんなことを知ることができた。」なんてよくある話なんですよね。
写真は段ボールでつくったピザ釜で、ピザを焼いてるところです。 (写真4枚)




学習共同体河浜塾「星降る一夜合宿」その1
2014年9月1日会長
かささぎのわたせる橋に置く霜のしろきを見れば夜ぞふけにける
ちょっとロマンチックな授業のあとは。河浜塾恒例「星の動き体操」をしました。



会長・河浜の講話
2014年8月11日会長
夏期講習会の前半が終了しました。この前半の授業の中で一斉指導教室の全中3の授業中、20分という短い時間でしたが会長・河浜が講話を行いました。そして、その講話は多くの生徒に感銘を与えたようです。そこで、スケッチブックの巻頭に収めたく、講話の内容を原稿に起こしましたので、ここに掲載いたします。
河浜:中3のみなさん、今日は20分の時間をとって講話をいたします。何故、今日という日を選んでみなさんにお話をするのか、それには意味があります。
みなさんに質問いたします。みなさんの人生はいつ始まりましたか?もっと詳しく言うと、みなさんが「自分の人生を生きよう」と思って人生を歩み始めたのはいつですか?
おそらくは「自分の人生」なんて考えて小学校を歩んできた人は一人もいないはずです。小学生って子供ですから、何も考えずにただ生きていただけではないですか?「俺の人生は?」なんて考えている小学校1年生がいたとしたら、ちょっと気持ち悪いくらいです。(笑)
みなさんはたまたま生まれた場所・育った場所で自然に通う小学校が決まっており、たまたまそこで知り合った友達と自然に今日までを歩んできたはずです。わたしも同じです。わたしは小さい頃貧しい家庭で育ちました。当時の河浜の家は、元々一つの家庭が住んでおられた木造3階建ての家の2階部分だけを間借りしていたんです。1階にも3階にも別の家庭が住んでおられました。だから我が家では、3軒の共同台所・共同トイレしかありませんでした。風呂は銭湯・河浜の部屋は雨漏りすることもある屋根裏部屋でした。でもちっとも辛くはありませんでした。だって、そんな状態が生まれてきた自分に与えられた環境であり、何の疑問もなく、特にそのことをどうのこうのと考えることもなく、それが当たり前のように過ごしていました。むしろ、父と母の愛情に満ちた家庭で育てられたことは楽しいことでした。共同台所で、3軒の奥さんたちが並んで夕飯の支度をしていると、ちょっとつまみ食いをさせてくれたり、激しい雨が降る日にはきゃあきゃあ言いながら雨漏りの下に「たらい」や洗面器を置いていったり・・・それは何にも考えずに済む幸せなのんびりした日々だったのかもしれません。
ところが中3になったある日、「お前はどこの高校に行きたいんか?」「お前は大きくなったら何になるんや?」という自分の人生に関わる問いを浴びせかけられたんです。それはちょうど中3になった、みなさんの今に当たる時期でした。
すなわち、みなさんは今という時期に初めて自分自身の意思で自分の人生の扉を開こうとしているんです。しかも、それは自分の力で開かねばなりません。みなさんは今、自分で切り開く人生のスタートラインに立ったのです。
さて、そんなときみなさんは、この塾に通っています。この塾ではもちろん合格するための知識を伝え、問題を解く方法を教えます。それはそういったことを伝えないと合格しないからです。みなさんを合格する状態にして試験会場に送り出すことがわたしたちの仕事です。でも、そんな知識の多くを皆さんはいずれ忘れてしまいます。今ならっている化学式や歴史の知識などをいつまでも覚え続けている人はほとんどいません。たとえば自分の職業に関係のある知識や社会で生きていくために必要な知識は大人になっても忘れないでしょう。でも多くの知識は頭に残りません。
ただ、高校入試の時期に「一生懸命に頑張った事実」・頑張ったことによって得られる「努力の方法」・頑張った事実によって得られる「自信」は、これから先何物も奪うことのできない経験となって、みんなの心に残るはずなのです。
この塾では、多くの卒業生が卒業後もつながりを求めて訪ねてきます。先日も卒業生同士のカップルが、婚姻届の立会人の印を押してほしいとやってきました。彼らは言います。「ここは、僕らの頑張り人生をスタートした場所です。」と・・・。
そうです。わたしたちは、努力家を育てたい。そして、そういった頑張り人生のスタートラインがこの塾であってほしい。それがわたしたちのつくりたい塾であり、中3という「自分で扉を開く人生のスタート」で改めて皆さんに意識してもらいたいことです。
自分の力で歩み始めるこの時期、学習共同体というこの塾で、高らかに宣言して自分の人生を始めようじゃないですか。今をそのスタートラインにしようじゃないですか。努力する人生のスタートライン、それが学習共同体という「情熱の学び舎」なのです。